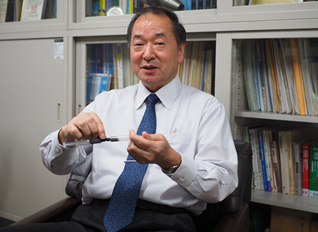File.09「賢い流体」で高度な制御を実現する

機能性流体とは、油などの液体にさまざまな微粒子を混ぜるなどして、目的となる性質を持たせた流体だ。
とくに先生が研究しているのは、「ER流体」や「MR流体」と呼ばれるものになる。ER流体は電場を、MR流体は磁場をかけることで、
液体の粘り気や硬さをコントロールすることができる。写真で先生が手に持っているのが、黒いMR流体の入ったシリンダーだ。
磁石を近づけると、それまでスムーズに動いていたピストンがまったく動かなくなる。
このMR流体の性質を使って実用化を進めているのが、免震・制振装置だ。
これは地震の時に建物の揺れを抑えるため基礎や柱の途中に設置されている装置で、免震では積層ゴム製のものが多く、
制振では一般的な油を使ったダンパのものが多い。積層ゴムは地震動を逃がすだけだが、MR流体ダンパと組み合わせて使えば、
揺れを検知すると、それを抑える方向に力をかけることができる。より賢く建物の揺れを制御できるというわけだ。
●より自然な義足を開発
さらに中野先生は、MR流体を福祉分野にも応用しようとしている。たとえばけがをして足が動かせなくなった人のリハビリのために、
強制的に足を動かす機器がある。だが従来のものは力のかけ方が単純なため、人の動きが機械と合わなかったりしても微調整ができず、
危険が生じる問題があった。MR流体を利用したクラッチをモーターに組み込めば、人の動きに合わせた動かし方ができるようになる。
さらに産業用ロボットに応用すれば、力の強いロボットが勢いで人を傷つけるような事故もなくせるという。
また義足への応用も研究中だ。MR流体ブレーキは小型で大きな力を出せるので、膝に組み込めば、椅子に座る時の中腰の姿勢のような、
大きな力が掛かる状態もキープできるようになる。現在の義足の動作には制限が多いが、MR流体を利用すれば、
より自然な動きができる義足も開発できるだろう。
一方、ER流体は電場を掛けるだけで力を発揮できる。つまり、2つの電極さえあればよい。
そのため装置を簡単かつ小型にすることができる。MEMS(メムス)と呼ばれる、超小型機器への応用が可能になるといい、
現在、点字表示器の開発に成功しているそうだ。
専門のかけ合わせが強みになる
研究では「固定観念にとらわれないこと。食わず嫌いをせず、いろんなものに興味を持ってほしい」とのことだ。 専門分野については深く掘り下げつつ、視野は広く持ち続けることが大切だ。さらに専門分野は1つだけではなく2つ以上あれば、 独自の強さを持てるだろうという。違う分野の人とのコラボレーションも相乗効果があり、よりよい成果を出せるだろうということだ。

先生は体を動かすのが好きで、山形大学にいた時はスキー場が近くにあったため、子供と一緒によくすべりに行っていたそうです。 今は毎週テニスクラブに通って汗を流しているとのこと。同年代でさまざまな立場の人たちと交流できるのも、 テニスクラブの楽しさの一つだそうです。