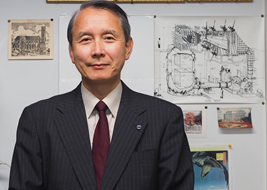File.10流体の機能性で環境問題に切り込む

西山先生が取り組む「機能性流体」は名前のとおり、気体や液体に目的に応じた特別な機能を持たせたものだ。
先生は機能性流体の中でもとくにプラズマ流体と磁気粘性流体(MR流体)を駆使して、環境や安全に関する課題解決に取り組んでいる。
プラズマ流体の中には、マイナスの電荷をもった電子と、プラスの電荷をもったイオンが一緒に存在している。
このプラズマ流体は強力な酸化効果をもつ。そこでとても小さな気泡内にプラズマを発生させて廃水に混ぜ込めば、水中の汚染物質を分解することができる。
工場排水や魚を処理した後の水、畜産農家における脱臭などへの利用が可能だ。さらに医療系の廃水、つまり抗生物質やVOC(揮発性有機化合物)、
人が飲み込んだのち排出される薬の成分など、一筋縄ではいかないやっかいな成分も処理できると期待されているのだ。
●人にやさしいプラズマでPM2.5の空気をきれいに
西山先生は次世代プラズマエアコンやプラズマ加湿器の開発につながる技術も研究中だ。気体を通過させるチューブの内部にプラズマを発生させ、
PM2.5のような小さな粒子を詰まらせずに運んだり、プラズマによって発生するオゾンで、
粒子表面についている汚れやチューブ内につく小さな液滴内部の汚れを取り除くことができるという。
一方、MR流体は簡単にいえば油の中にとても細かい鉄粉を混ぜたものだ。磁場をかけることによって、どろどろになったり、
さらさらになったりというように粘り気を変化させることができる。この性質を利用して、配管の破損した部分にMR流体を導入し、
磁場をかけて固めると、穴をふさいで漏れを止めることが可能だ。溶接など従来の方法を使うと後でやり直すことは難しい。
MR流体であれば磁場をかけるのをやめれば元に戻る。そのため後で別の方法で修理し直すといった臨機応変な作業が可能だ。
これらの機能性流体は、電場や磁場をかけることによって性能を発揮する。省エネが求められるなか、
できるだけ小さなエネルギーで最大の機能性を得るような工夫を追求しているそうだ。
異文化との交流で新しさが生まれる
先生が積極的に取り組むのが海外研究者との共同研究だという。異なる背景を持った人たちと一つのことを進めていくのは大変だ。 ときによっては忍耐が欠かせないという。だが多様な人たちとなんとか工夫をしながら研究をすすめていると、ふっとかみ合う瞬間が訪れるそうだ。 そうすると全く予想もしなかった方向性が見いだせたり、新たな楽しさが生まれてきたりするという。

西山先生は歴史探訪が好きとのことです。たとえば山城で人々が戦ったりしていた様子を想像すると、過去から今までの自分とのつながりが感じられて、 元気をもらえるそうです。流体の研究者だからか、歴史の流れを意識したり、川のそばに住むなど、流れを意識することが多いようです。 写真は川を背に剣道の上段の構えを取っているところで、腕前は有段者だそうです。