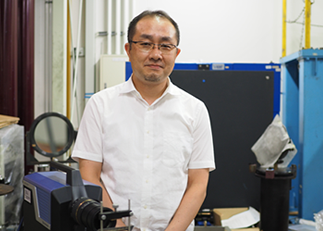File.24マイクロ秒でみる衝撃波の世界
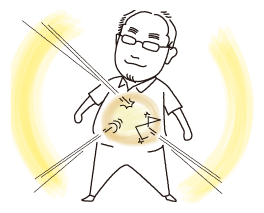
衝撃波とは、音波よりも速く進む圧力の波のことだ。超音速飛行機や隕石、宇宙から帰還するスペースシャトルなどによるものが有名だろう。
超音速機のように音速を超える物体の移動によってつくられ、急激な高圧、高密度、高温の波として伝わる。
超音速機では騒音を引き起こすなど問題視されることもあるが、一方で積極的な利用も行われている。
例えば開腹手術をせずに体内にある結石を取り除く方法として、体の外から衝撃波を結石に当てて破砕する治療が確立法されている。
現在、大谷先生が医学部と協力しながら取り組む研究の一つが、衝撃波の体内における伝播メカニズムの解明だ。
爆発現象においては、発生する衝撃波が人体内部でダメージを与える。
生体の内部は各部位によって物性が違うため、波の進むスピードや反射、透過の仕方も様々で伝播は複雑になる。
そこで先生は頭部のモデルを作り、内部における衝撃波の挙動を実験によって調べている。
観察の原理は暑い日の陽炎と同じで、空気の密度の揺らぎを撮影する。
ただし「衝撃波はマイクロ秒(100万分の1秒)の単位で考える世界です」(大谷先生)。
とくに波は、人体の主成分である水中において、空気中の4倍以上の速度で進む。
そのため観察が難しく、空気中の衝撃波ほど研究は進んでいない。
「衝撃波は実はあらゆる流体現象に伴って発生する現象です」と大谷先生はいう。
伝播のメカニズムの研究が進めば、爆発に対する防護だけでなく、さまざまな応用につながるかもしれない。

衝撃波の研究装置は基本的に大掛かりで、それぞれの目的を持った設備が各地にあります。 そのため出張も多いとのこと。写真は流体科学研究所 衝撃波関連施設でトロンボーンの衝撃波を撮影したものです。 楽器によって生じる衝撃波を動画で撮影したのは、この時が世界で初めてだったそうです。