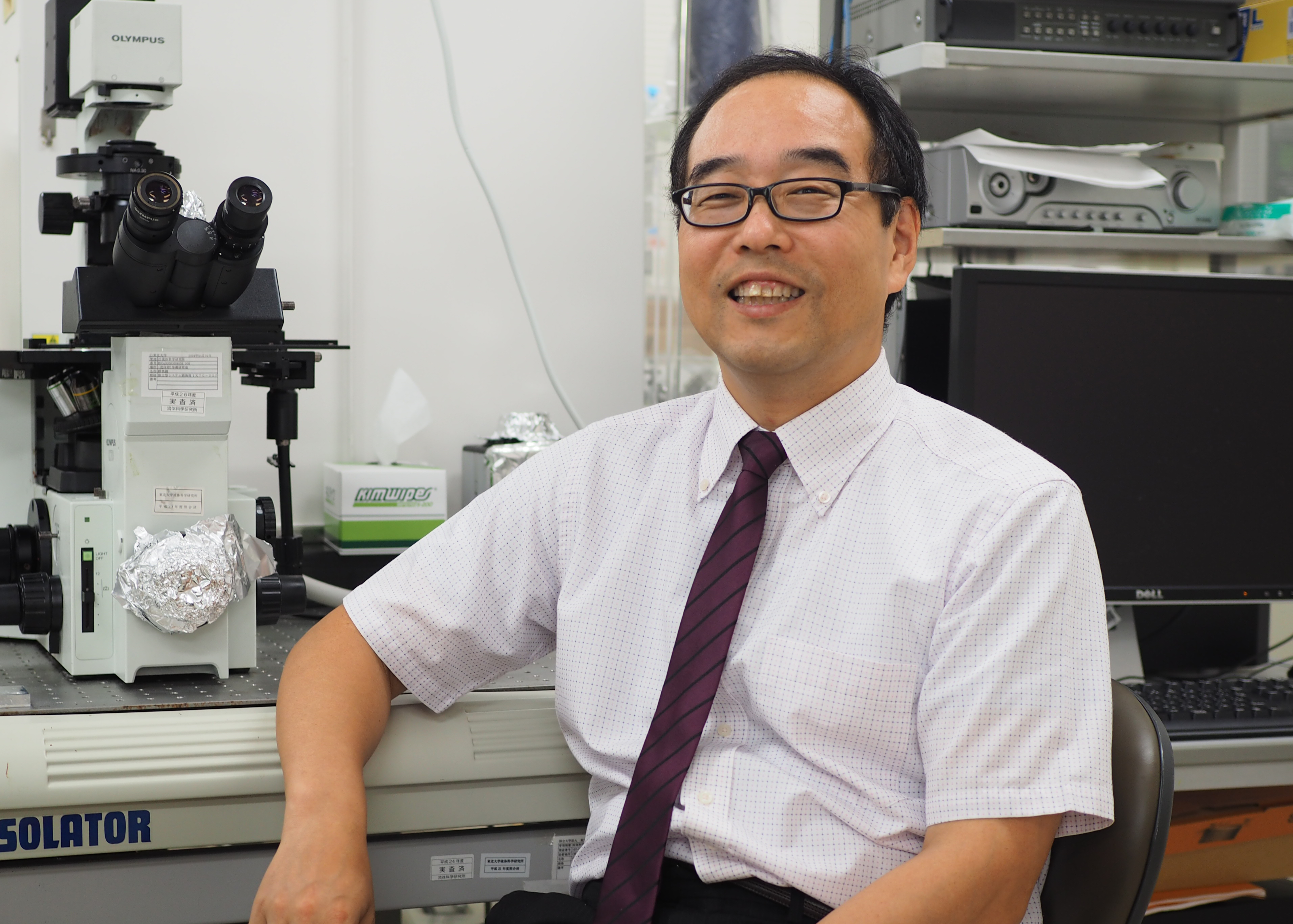File.28人体の免疫機構の秘密を探る

生命維持のメカニズムの解明において、血液の流れを読み解くことはとても重要だ。白井先生は、白血球の一種である好中球の流れに着目し、実験とコンピュータシミュレーションの両面から研究を行っている。白血球は人体を病気から守る免疫機能を持つ血球で、好中球はその中で最も数が多い。
好中球の濃度は、場所によって異なることが以前から知られていた。特に濃度が高いのが、毛細血管のあとに続く細静脈と、肺胞の表面を覆う毛細血管網だ。濃度が高いと外敵をやっつけるのに都合がよいものの、好中球がどのようなメカニズムでこれらの場所にとどまっているのかはわかっていなかった。
細静脈については、その太さが毛細血管より一回り大きくなる。そのため、毛細血管を出てきた赤血球が細静脈の中心を勢いよく流れ、好中球は血管壁に押し付けられる。白井先生らは、この押し付けが濃度の高くなる要因の一つではないかと考えた。そこで遠心力によって血管壁への好中球の押し付けを再現できる傾斜顕微鏡を開発、細静脈の内壁を再現した模型を作って実験を行い、赤血球による押し付けが好中球の動きに与える影響を明らかにした。
一方、肺胞の毛細血管網に好中球がとどまる理由は、細静脈の場合とは異なる。毛細血管網は非常に細く複雑なため、好中球は引っかかったり詰まったりしていると考えられるのだ。こちらについてはシミュレーションを行っており、実験の結果と比較しながら実態を明らかにしていきたいということだ。

休日は家族で出かけたり、お子さんとゴルフの打ちっぱなしに行くこともあるそうです。写真は農作業などの体験が行える秋保ヴィレッジで田植えをしているところ。お子さんは田んぼに入るのが初めてで大はしゃぎだったとか。案山子づくりや稲刈りも体験し、次は精米の予定だそうです。