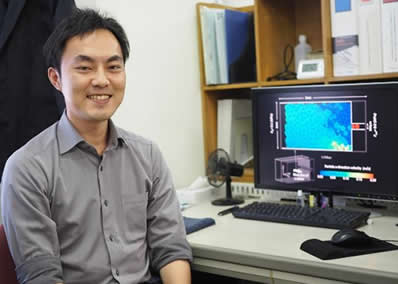File.32地中深くの現象を可視化する

トンネルを作ったり石油を掘ったりするときは、地盤が変形したりひびが入ったりする。
だがその様子を直接見ることはできない。清水先生はそんな地盤材料の破壊現象のコンピュータシミュレーションに取り組んでいる。
先生が用いるのは「個別要素法(DEM)」という方法だ。この方法は、たくさんの粒子をばねでつなげることによって地盤を表現する。
例えば粒子同士をつなぐばねを強くすれば硬い地盤と考えることができ、弱くすれば柔らかい地盤を表現できる。
水を含むと膨張するような地盤は、粒子を膨張させるといったことで対応できる。
この方法の特徴は「変形が起こった原因が分からなくてもシミュレーションできること」(清水先生)だという。
ボールの動きを計算したいときはニュートンの運動方程式を使うように、地盤の変形を方程式で計算するという方法もある。
ただし方程式が使えるのは、地盤がどのような理論を元に動いているのかわかっている時だけで、未知の動きには対応できない。
一方DEMは、どんな仕組みの動きでも表現することができる。そしてその結果から、実際の地盤で何が起きたかを推理することが可能なのだ。
「高校の物理で習う単純なばねの接続で、現象の本質に迫ることができる」と先生はDEMのおもしろさを語る。
先生は火山のマントル付近で化学反応によって発生する亀裂や、放射性廃棄物の地層処分などにも取り組んでいる。
DEMは避難誘導時の人の動きや星の動きの研究にも使われており、アイデア次第で様々な応用が可能な手法だ。
今後もDEMによってどんな現象が解明されるのか楽しみだ。

先生のモットーは「やるならとことん」だそうで、例えば大学の長期休暇の時はひたすら一つのことに没頭していたとか。 休暇のたびにバイクで日本全国を走り回ることが多かったそうで、大学のあった京都から北上し、 フェリーで海を渡って北海道を目指したりしていたとのことです。