File.54次世代の航空機づくりはどんな形?
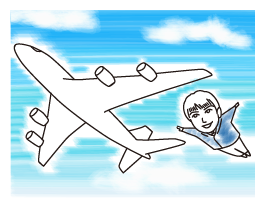
飛行機をつくるためには風洞実験や飛行試験などが欠かせない。しかし大掛かりな試験にはかなりのコストが掛かる。そこで活用されているのが、コンピュータシミュレーションだ。とはいえシミュレーションにも大きな課題がある。飛行機はさまざまな物理現象が作用し合った結果、空を飛ぶ。この複雑な現象を正確にコンピュータ上で再現するのが難しいのだ。
例えば飛行機が飛ぶ様子は流体力学、機体の変形や破壊は材料力学によって、それぞれ高い精度でシミュレーションが可能である。だが実際は、流体の力が機体を変形させ、また機体の変形が空気の流れに影響をおよぼすというように、お互いが作用し合っている。こういった異なる分野のシミュレーションソフトウェアを、精度を維持したまま連携させるのはまだ難しいのだという。
阿部先生は、各シミュレーション同士を高精度かつ高い計算速度のまま連携できる、新しい「マルチフィジックス」技術の研究に取り組む。特に最近の航空機製造においては、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の採用や、3Dプリンタの活用など、新しい材料や加工法が注目されている。先生は将来、航空機のモデルを丸ごとコンピュータ上に構築し、飛行性能や新材料、加工法などあらゆるバーチャル試験が可能なシミュレーション環境を実現したいという。
また航空機の物理の統合的な理解を進め、「航空機物理学」と呼べるような新たなジャンルを確立したいとも語る。次世代の航空工学を見据える先生の研究に大いに注目したい。
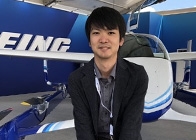
先生は子供の頃から飛行機が大好きだったそうです。飛行機に初めて強いあこがれを抱いた記憶は、旅行で飛行機に乗った幼稚園児の時のこと。以来、飛行機少年になり、大学でも迷わず航空機に関係する学科を選びました。中でも「つくる」ことに携わりたいと、現在の研究に進んだそうです。
