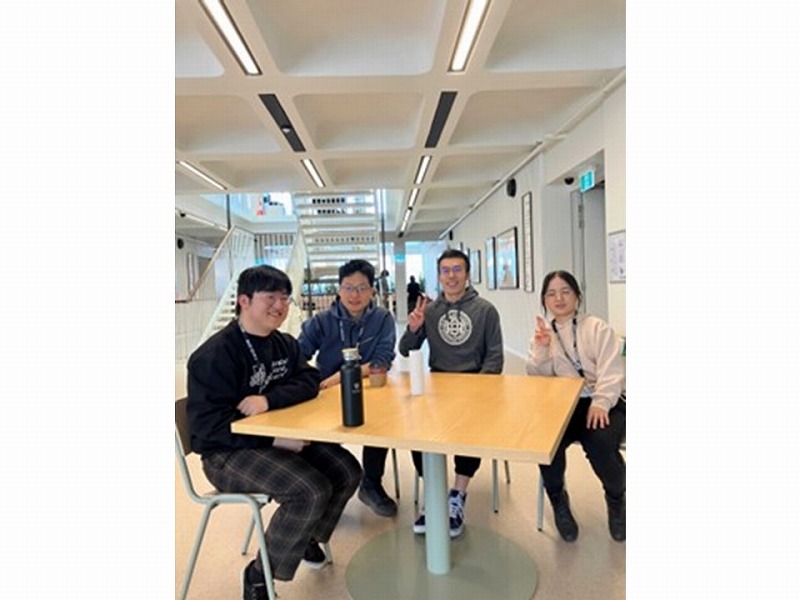Event2024イベント2024


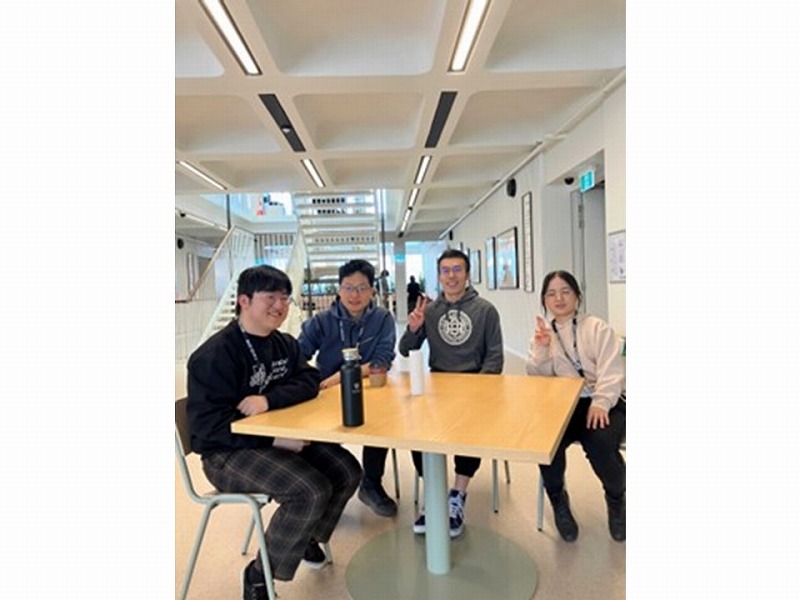




オーストラリア留学
最近、スーパー(マーケット)好きがばれてきている、D2小泉です。9月下旬、およそ1年間の行っていた、オーストラリアでの研究留学を終えましたので報告いたします。
今回の留学はGP-Mechの国際共同研究プログラムによるものでした。GP-Mechは高等大学院機構内の国際共同大学院プログラムの1つで、海外の研究グループとの国際共同研究を通じて国際社会で活躍する人財への成長を促しています。私は、自然対流の研究が盛んなオーストラリアにある、The University of Sydney(USYD)とThe Australian National University(ANU)の2つの大学での研究をしてきました。
前半5か月、USYDでは主に数値シミュレーションを行いました。オーストラリア、ニュージーランド、インド、ブラジル、ロシアといった多国籍の研究者らと共に研究する機会に恵まれました。彼らは主に数値シミュレーション手法の開発に注目している、ユーザーとは別の視点を持った研究者であり、私自身も新しい視点を持つことができたと感じています。2か月に一度開催された研究MTGは、普段日本の研究室でやっているそれとは異なり、学会発表のように10分程度のプレゼンを行いました。研究内容はもちろんのこと、発表スライドの作り方や発表時の英語など勉強になることがたくさんでした。
後半7か月、ANUでは数値シミュレーションを続けながらも、主に実験を行いました。USYDとは異なり、中国をはじめとする多くのアジア人学生が在籍しています。彼らは主に、熱応用に関する研究を行っており、扱っている現象そのものについて議論を深めることができました。ここでは週に一度MTGがあり、各研究者・学生間の情報共有が活発でした。また、MTGを行う部屋の広さの関係上、物理的な距離も近く、各自の発言のハードルが低かった印象があります。
昼食を同僚ととることはコミュニケーションの機会をできるだけ多くとるために1年を通して力を入れていたことです。これによって英語力の向上が実感できた他、食事や休日の過ごし方、買い物の仕方など他国の文化を学ぶことができました。また、ここで仲良くなった同僚と休日過ごすことができたのもいい思い出です。
ちなみにオーストラリアは自然が素晴らしかったです。Blue mountainsは、まるでモンハンに出てくるかのような壮大さがあり、Bondiをはじめとするビーチは砂が白く鮮やかな青の海が魅力的でした。
最後に、研究、金銭、また精神の面で支えて頂いたみなさま、感謝申し上げます。
D2 小泉匠摩