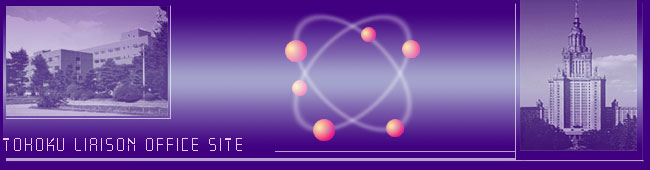|
リエゾンオフィス・ニュースレターNo.5
2002年10月20日
9月で東北大学リエゾンオフィス1周年
1.日本学術振興会 古川氏、樋口氏が東北大学リエゾンオフィスを訪問
9月25日、日本学術振興会研究協力課長古川佑子氏、同国際研究協力課協力事業係長樋口和憲氏がリエゾンオフィスを訪問した。ヴァシリエフ教授と面会した両氏は、リエゾンオフィス、モスクワ国立大学キャンパスを案内された。両氏はヴァシリエフ教授が学科長を務める低温物理学科の研究について説明を受け、研究施設、講堂等の見学をした。
古川氏らのモスクワ訪問の目的の一つは、ロシアの研究者が政府のプログラムの下で他の国とどのように共同研究を組織しているかを調査し、日本学術振興会の事業によるロシアと日本の共同研究の可能性を見出すということであった。
2.ロシアにおける東北大学の2つのリエゾンオフィスの協力関係始まる
9月28日、東北大学東北アジア研究センターの職員、事務局の職員、同研究センター・シベリア連絡事務所の駐在員からなる代表団がモスクワのリエゾンオフィスを訪問した。
東北アジア研究センターは1996年、東北大学の研究施設として発足した。同研究センターは、東アジア、北アジアと日本を含む東北アジアの地域研究を学際的に行う研究機関として位置づけられ、世界的な研究センターとなることが期待されている。1998年にはロシアのノボシビルスク市に東北大学初の海外拠点となるシベリア連絡事務所が設置された。同連絡事務所の設置目的は、ロシア科学アカデミーシベリア支部の75の研究施設と東北大学との間の学術的な情報交換を促進し、共同研究プロジェクトを行うことである。
代表団はリエゾンオフィスで、リエゾンオフィス共同顧問会議のメンバーであるヴェダイェフ教授とリエゾンオフィス職員のヴァシリエファ夫人に面会した。代表団長は文学部事務長の佐藤正義氏。佐藤事務長と代表団のメンバーはヴェダイェフ教授にシベリア連絡事務所の運営について説明し、ヴェダイェフ教授はモスクワ・リエゾンオフィスの運営について代表団に説明した。この話し合いを通して、両者はロシア国内にある二つの東北大学リエゾンオフィス間の緊密な協力関係を構築するべきであるとの見解に達した。この問題については既に、2002年6月の阿部総長率いる東北大学代表団のモスクワ国立大学訪問の際にも議論されていた。東北アジア研究センターからは佐藤源之教授と塩谷昌史助手がその時の代表団に加わっていた。佐藤教授らは両リエゾンオフィス間の協力の可能性について話し合い、この時が東北アジア研究センターの教職員がノボシビルスクから仙台に帰任する途中にモスクワ国立大学のリエゾンオフィスに立ち寄る最初の機会となった。
東北アジア研究センター代表団は低温物理学科にあるリエゾンオフィスだけではなく、モスクワ国立大学本館も訪問した。一行は講義室、モスクワ国立大学学術評議会の会場となる、座席数1000席以上ものメインホール、そして日本からの留学生や講師の協力を得て行われた日本語によるコンサートが当日開催されていた文化センターを見学した。
その後、一行はアジア・アフリカ研究所、日本語学科長のユージニー・マエフスキー教授と面会した。この会談は代表団の訪問が公務的な訪問だけでなく、興味深く有益なものとなるよう、特別に企画されたものである。
アジア・アフリカ研究所1956年に開設され、現在ではロシアの主要な東洋学研究機関となっている。同研究所はアジア、アフリカの国々の40以上の言語を研究している。教職員の数は250名。そのうち教授は30名、Doctor
of Science と PhD degreeを取得した助教授が70名。教職員の多くは東洋学の基礎研究と日本語、中国語、サンスクリット語、アラビア語、ペルシャ語、その他のアジア、アフリカの言語の語彙と翻訳において世界的に知られている。
アジア、アフリカ学研究所への訪問は、リエゾンオフィスの運営にとっても重要なことであった。というのは、両大学の共同研究を物理学分野だけからその他の分野へ広げるための第一歩だったからである。今回のこの訪問は、両大学間の協定にも明記されている文化的分野での協力関係における初めての実績となった。
 3.両大学の協力関係の実際的な成果
現在進行中の両大学の共同研究の例の一つとしては、モスクワ国立大学物理学部低温物理学科ヴァシリエフ教授と、東北大学流体科学研究所高木敏行教授の研究グループとの共同研究が挙げられる。ヴァシリエフ教授と高木教授は多くの実験を重ね、新規強磁性形状記憶合金の特性を研究している。この共同研究は1992年に始められたもので、これまでに20編以上の共著論文が国際的な物理学分野の学会誌に発表されている。両教授の共著による最新の解説論文は、形状記憶合金の問題について書かれており、ロシアの主要なレビュー誌の一つである『Advances
in Physical Sciences』誌に投稿中である。
ヴァシリエフ教授は、東北大学において、金属材料研究所、工学研究科の研究グループとも共同研究を進めている。2003年1月から4月にかけて、同教授は客員教授として東北大学に滞在する予定となっている。また、その際ヴァシリエフ教授は、高木教授との新たな機能材料の共同研究も進める計画である。
1998年にヴァシリエフ教授は、大学院生ヴラジミール・コバイロ君が高木教授の研究室での研究をするためのアレンジをした。流体科学研究所滞在中にコバイロ君は高木教授の研究グループのメンバーとともに形状記憶合金の特性に関する研究を行い、共著者として様々な学会誌に論文を発表した。今年コバイロ君は「強磁性形状記憶合金」の博士論文により日本とロシア両方の博士号を取得した。
4.この1年間を振り返って
2001年9月20日に東北大学流体科学研究所のリエゾンオフィスとしてモスクワ国立大学物理学部内に設置されたモスクワ国立大学内の東北大学リエゾンオフィスは、このほど1周年を迎えた。当初、部局間のリエゾンオフィスとして設置されたが、後に大学間レベルのリエゾンオフィスとなった。
この1年間を通して、60名以上の方々がリエゾンオフィスを訪れた。その中には東北大学の阿部博之総長、モスクワ国立大学のサドーヴニチィ総長、いくつかの政府機関の学術的な学会のメンバー、8ヶ国(日本、ロシア、アメリカ、ドイツ、インド、中国、英国およびイタリア)の大学、研究所の著名な科学者20名が含まれる。
両大学間の協力体制は、学術的な面のみならず、実際的な交流活動をも担っている。流体科学研究所と物理学部の研究者の共著により多くの学術論文が主要な物理学分野の学会誌に掲載された。2002年10月、モスクワ国立大学物理学部の学生2名が「東北大学短期留学生受入プログラム」に参加するため、仙台に到着した。
今後リエゾンオフィスは、科学、文化の両面で新規の共同研究プロジェクトを立ち上げるために、その活動を物理学部以外の学部にも広げていく計画である。
Edited by Vera Vasil'eva and Naoko EJIMA
<本ニュースレターの関連URL>
http://www.tohoku.ac.jp/index-e.html
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/index_e.html
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/
|